51『ミステリで読む現代日本』
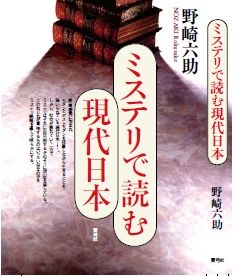
51『ミステリで読む現代日本』
青弓社 2000円 2011.11 ISBN978-4-7872-9203-2
280p
0章 AB-CD殺人事件
01章 小説は戦争に向かって慾情する
02章 壊れる人びと
03章 パノプティコンー流行する警察小説
04章 市民小説への道
00章 「九・一一」から「三・一一」へ
この一冊と52は、電子本化されている。サイトのリンクはつけない。
他にも、もう一点、電子本化されているが、書名は書かないでおく。
以上の三点は、書籍も電子版も同じ価格だ。常識的にはその分、著者印税の割合が多くなるはずだが、同じ10パーセントだ。それも一冊ずつの支払い。剰余価値で生じた「利潤」は、すべて中間搾取業者のほうに流れこむシステムだ。
本は著者と出版社がつくるものだが、これだと双方が損をする。読者も高い電子本によって損をする。このように、三方がそれぞれ貧乏くじを引くというつまらない文化生活が現実のものとなった。
この歪つなシステムが明瞭になったのは震災後だ。復興がビジネスになり、本を制作することとはまったく無縁なサービス業者や官僚が利益を横取りするようなルールが実体化してしまった。
その実例を自ら体験させられた。
電子出版の明るいほうの話題については、「マガジン航」に書いている。
わが「キンドル作家」デビュー実践記 執筆は、2014.3。
これは何故か、執筆リストに書きもらしていた。他にも記入漏れ・チェック漏れがありそうで怖ろしい。
下に、谷口基による書評を貼りつける。一読してどうもよくわからなかったが、再読してみても、やはりわからない。結論は、〈ネタバレ〉批評をやらねばミステリ評論のゴジラ蜘蛛の巣を払うことはできない、となっているみたいだが、本当に本心なのかねと疑ってしまう。
読者にネタバレと感知させないネタバレ叙述法の高等テクニックを駆使したいんだが、うまくいったとしても、その奥義を読み取ってくれる「高等な」読者はどこにいるのか。
谷口基 文学史を読みかえる・論集1 2012.8 インパクト出版会
本書は長きにわたり「ミステリ」を通じた社会•文化批評の論陣を張ってきた野崎氏の、最新の長編評論である。そのテーマはタイトルにも端的にあらわされているように、「ミステリを通して現代社会を考える試み」である。構成は以下の通りだ。
0章 A B— C D殺人事件
01章 小説は戦争に向かって慾情する
02章 壊れる人びと
03章 パノプティコンーー流行する警察小説
04章 市氏小説への道
00章「九•一一」から「三・一一」へ
野崎氏のミステリ評論の大きな特徴であり、同時に最大の魅力ともいうべき要素として、ジャンル意識を脱した広範な視野を基底におく論旨の展開があげられる。換言するならばそれは〈従来ミステリの範疇に入らない作品をミステリとして論じる行為〉のことであリ、大著『日本探小説論』 (水声社 )刊行前後から、ミステリ愛好家たちの間でしきりと批判の的とされてきたスタイルでもある。評 者はかつて、このスタイルを全面的に肯定し、その姿勢を高く評価してきたが、本書を読み進む 過程において、以前には感じられなかった違和感にとらわれた。
各章における試みは、時を得た明瞭な目的意識に支えられている。0章ではポストモダニズム的ミステリ批評の行詰まリを指摘し、01章では九〇年代以降のミステリに描かれる「戦争」の変容を辿り、02章では尖鋭化を志向しすぎて「壊れた」ミステリ・ジャンルを批判し、03章では盛況をきわめる「警察小説」のシビアな分析を行い、04章では「市民」の立場から犯罪と法を逆照射する新ジャンルを <発見 >し、 00章では「誰もが書き急いでいる」 3・11をミステリの側面から歴史的に総括すべき試みの序曲が奏でられている。
二十一世紀もはや十年を過ぎた現代日本の世相、人心、社会構造の忌まわしく微妙な変形をとらえるべく、野崎氏の闊達な箪は縦横に飛ぶ。そこに引用された驚くべき広範にわたる「ミステリ」の数々にまず、読者は瞠目するだろう。しかし、「何かがくいちがっている」。その理由はふたつあると思う。
ひとつめは全六卓、各章の緊密度が捉えにくい、ということだ。たとえば野崎氏は「はじめに」において記している。
0章は、準備段階として、近年の議論によって明瞭になってきた原理論をまとめてみた。ミステリにあまリ翳染みのない読者には楽しめないかも知れない。飛ばして先に進んでもらってもかまわないが、いくつかの布石は施してある。とくに04章との関連で 〈二度読まれる〉ことを想定した章である。
同章においては主として、バイヤール による古典ミステリのパロディ的批評 (クリスティー、ドイルらの古典的名著を本歌取りしつつ、原典では名指されなかった「真犯人」をテキスト論に基づいてつきとめるという試み=ポストモダン的「再読」)を紹介し、ミステリに対するポストモダニズム的批評の限界について論じている。同時期に刊行された笠井潔『探偵小説と叙述卜リック』 (東京創元社)でも採り上げられたこのテーマは、 野崎氏の要領を得た筆致と説得力ある分析で、なかなかに読ませる一章を構築し、「愉しめない」などという批判はあたらない。
だが全章を読了したのちに、同章の役割とははたして何であったのか、と顧みると、困惑せざるを得ないのだ。0章の断ち切ったような終わり方は、次章以降へ架橋されるはずの本書総体に関わる大きなテ—マについて、読者の意識を牽引していく道をも断ちきってしまっているかに思われるのだ。野崎氏が示したように、0章が 04章4の布石であるとするならばーーすなわちポストモダニズム的ミステリ批謗ならびにそれを許すミステリ・テクストへの批判と、現代日本における犯罪•報道・裁判から紡ぎ出される言語空間との関係性を対照させていくという図式が本書の要諦であるとすればーー評者のごとく凡庸な読者には、その画期的な図式があいにくときわめて見えにくくなってしまっているのである。
暴論を承知で私見を述べさせてもらうならば、0章と04章 4はもっと緊密に関連づけてほしかった。何故ならば04章 4こそが本書の圧巻、「再読」というポストモダン的行為と、「再読」を促しつつも「再読」を遮る言説をつくりあげてしまう実在の重大事件とその裁判をめぐるおそるべき言語環境との対比がそこでは展開されるからなのだ。ここにこそ野崎ミステリ論の真骨頂があるからなのだ。
ふたつめは、野崎氏一流のジャンル横断意識とアクロバティックな展開におぼえた一抹の疑問である。再度「はじめに」より、論の前提を確認しておく。
(前略 )本書が主要に考察対象とするのは、ミステリにおそらく限定される。ただ、通常はミステリとみなされない作品も混在してくる。とくに原則はもうけていない。また、通説との異同についても、いちいち断っていない。推理小説、もしくは探偵小説など、呼称は数種あるが、本書ではごく大ざっぱにミステリと表記する。この用語に特別執着しているわけではない。曖昧さを気取っているのではなく、ジャンル分類の崩壊もまた、本書のテーマに付随してくる。そうした条件の結果だ。
「原則」はもうけず、「特別」な「執着」があるわけではない。つまりは、「ジャンル分類の崩壊」を「現代日本」における文化の変形を象徴するひとつの現象としてとらえることに野崎氏の狙いはある、と受け取ることができよう。これは納得できることだ。探偵小説が偏狭きわまる再編成を受け、推理小説となり、その推理小説は社会派ミステリの登場によって推理に特化された世界観を捨て、ミステリという、エンターテインメント文学を総括する存在に生まれ変わった。統合からふたたび拡散の道を選んだミステリジャンル。その不安定な変容の歴史を知悉するゆえ、野崎氏はこれに対する「執着」から意識的に距離をおいて評論活動を続けているのだ。時代とともに流動し変容するジャンルである探偵小説、推理小説、ミステリにはそもそも、原則論は無用である、と。
しかし、凡庸なる読者である評者はあえて問いたい。ミステリという「呼称」に対してはかくもおおらかな野崎氏が、何故にミステリを批評する際の「原則」は遵守されるのか、と。
すなわち、圧巻の 04章 4「被害者の事件と加害者の事件」——光市事件に取材したミステリ作品 (薬丸岳『天使のナイフ』、深谷忠記『審判』 )において、「少年法」のあり方から「人間の罪と罰といった本源的」なテ—マにいたるまでのあまりにも巨大な問題に対し、創作家たちが「脳漿をしぼって」想到した結末についての紹介が <ネタバレ法度 >というミステリ評論界の不文律によって無惨にも阻まれていることはあまりにも、惜しい。
ミステリ愛好家は<ネタバレ>を忌み嫌うーーこれは常識である。山田風太郎『太陽黒点』廣済堂文庫版(一九九八年)の帯と裏表紙の惹句が真犯人を明示していたとしてファンの怒りを買った事件もまだ、記憶に新しい。だが、それだからこそ、原則論を批判する野崎氏には一線を越えてほしかった。
ただしこの要望は、評者が凡庸なる読者であると同時に、野崎氏にとっては嗤うべきポストモダニストであることを証明する。ミステリとは、真犯人さえ明白になってしまえば、「再読」されることのない消費文学であるのか ? この間いに対して否を言い続け、あえておのが評論においては <ネタバレ>を連発し続けている評者=野崎氏いうところの「ポストマン」は未だ消えず、今日もドアを叩き続けるのだ。
コメントを送信