平岡正明に関する七つのメモ3
『ジャズ宣言』1971.イザラ書房 増補版1979.5アディン書房 三版1990.10現代企画室

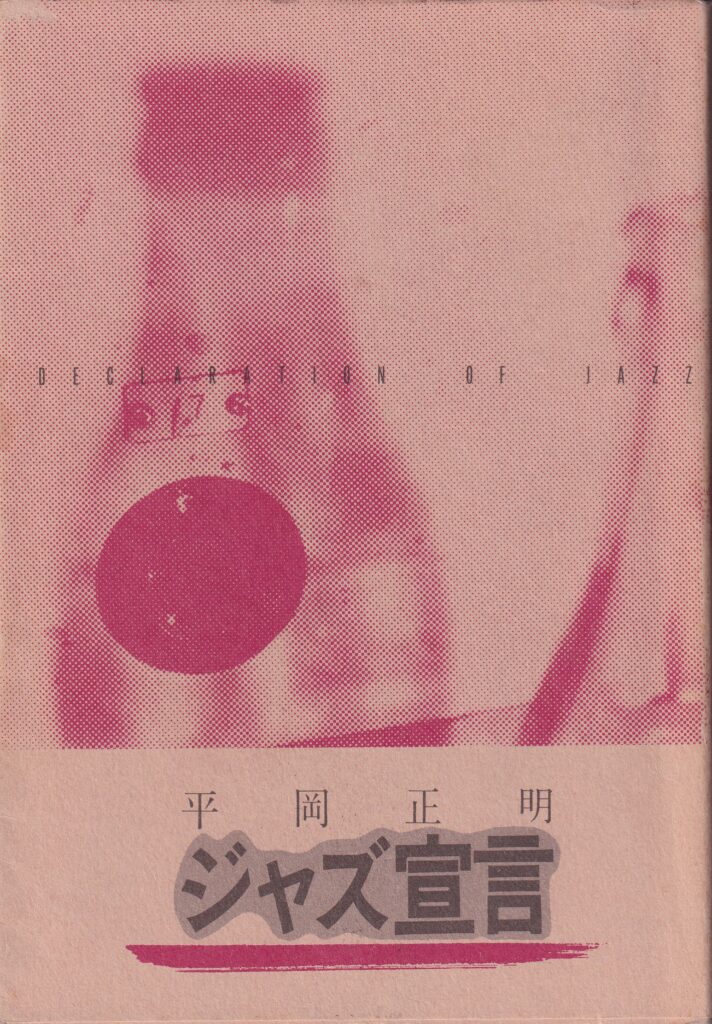
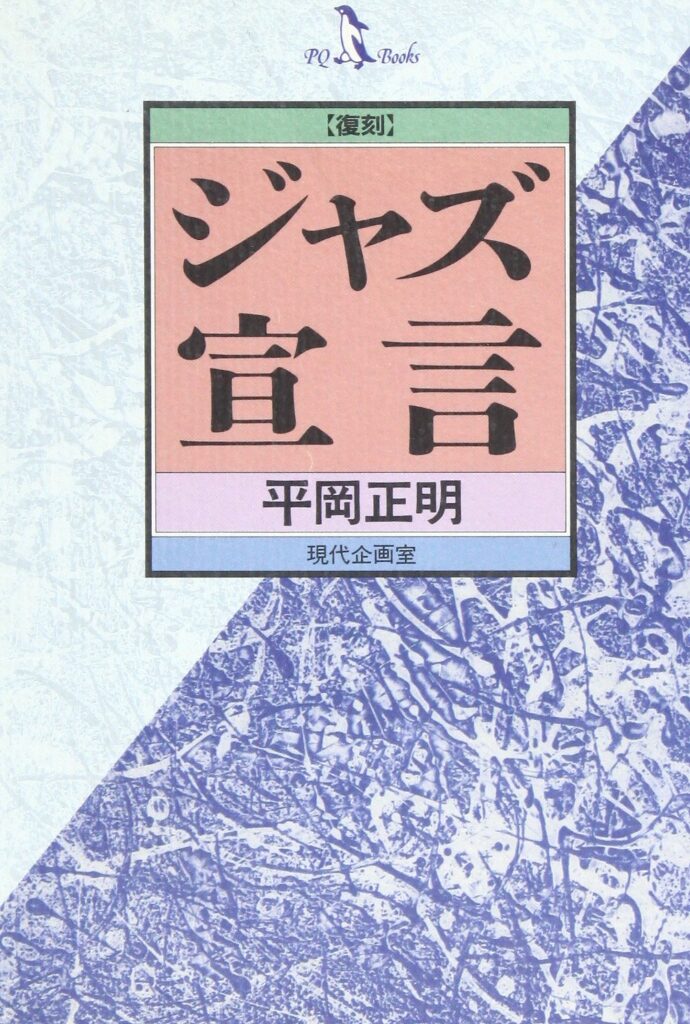
著者は平岡批判を引用して反批判を展開している。「批判文」は活字ではなく、ジャズ喫茶の便所の落書きから。第二版の185ぺージに写真がある。これらの「シーン」の全体が、表現者平岡の原風景となっている。
論争もまた、彼にとっては、フリースタイルのセッションだった。それなしには、ソロも成り立たない。論敵を「ぶっ壊す」などと過激な表明はあっても、論争の内実は、ステージを共にする「演奏者」への暖かみがある。
『ジャズより他に神はなし』1971.7三一書房

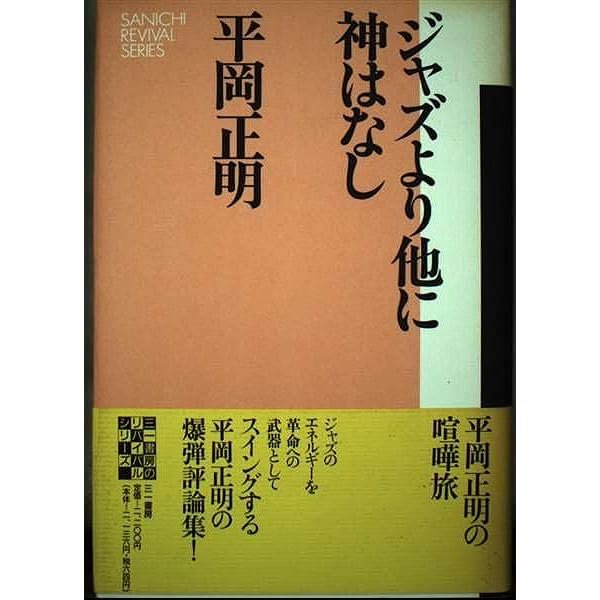
「あとがき」に《私の最後のジャズ書になる可能性が大きい》とあるが、そうはならなかった。主語が「私」なっている著者の表出に関しては要注意。
肩書きはジャズ評論家とされるのが一般的だ。
平岡の犯罪時評にあふれるディテールの「神」は、ジャズ評論においても、いっそうパワフルに発現してくる。ジャズを聴く鋭敏な「耳」のリポートに、黒人革命論・第三世界論・反植民地闘争論・世界革命論・階級闘争が怒涛のいきおいで流れこんでくる。だが、それらはたんなる外観にすぎない。
平岡の文体がアドリブ的であることは、誰しもが感じる。喋りがそのまま活字を呈して宙空をぶっ飛んでいく。論理的体系性はあっても、それらがいわゆる整序された流れをもって展開されることは、ごく稀だ。個人史ー個体史を縫って状況論・文化革命論などがカオスのように「演奏」されてくる。
遺るのは、ディテールの、シーンの輝きだ。
わたしが最も好きな平岡的シーンは、この本の140ページにある。「ジャズにとって日本六〇年代思想とはなにか」の原稿を持って、新宿駅に降り立つ著者。日付は六九年十月二十一日、《駅を降りると機動隊の解放区だった》。ーーこれが正確なリアリズムの情景であるかどうかは、どうでもいい。とにかく、このシーン、わずか数行の描写によって、六〇年代末の騒乱的激情のいっさいが、あるいは催涙ガス弾の飛来をともなって、まざまざと再現されてくるのだ。夢幻のごとくーー。
『毒血と薔薇 コルトレーンに捧ぐ』2007.7国書刊行会
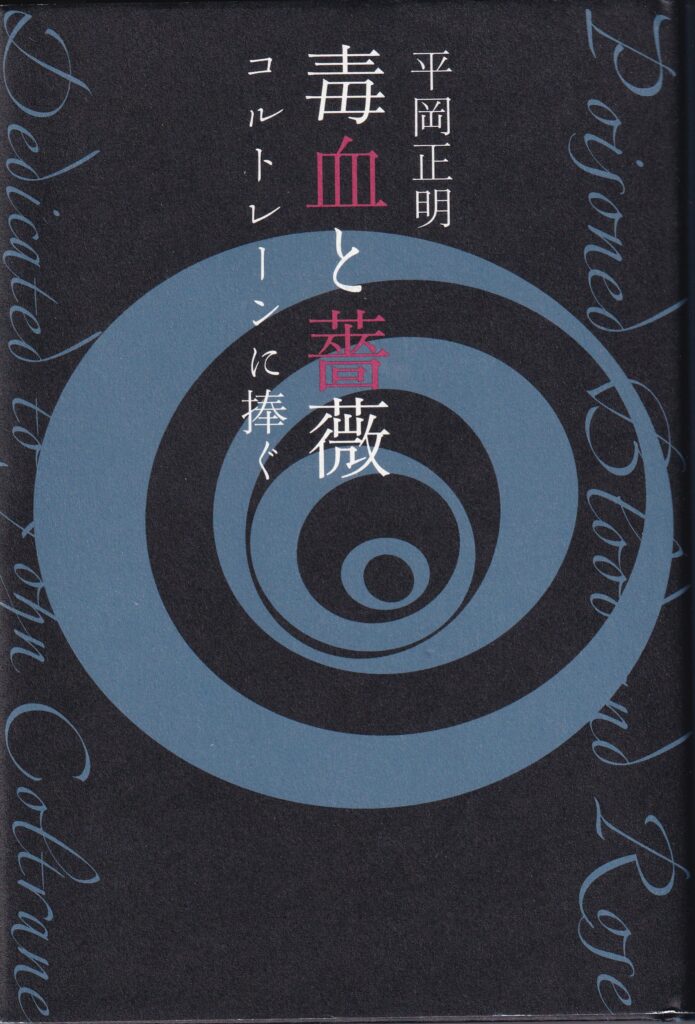
そして、ものを書くことは、ジャズとはかけ離れた孤独な作業だ。平岡は、ジャズはジャズ喫茶で聴くものだ、と主張する。それがジャズ体験であり、《家で聴くときは自分が邪魔だ》という。
この「自分」ーーエゴが、彼のなかでどう位置づけられているのか。書き疾走るとき、エゴが全開になる、というのは表面的な理解にすぎないのだから。
コメントを送信