セオドア・コーエン『日本占領革命 GHQからの証言』

第41回 セオドア・コーエン『日本占領革命 GHQからの証言』
著者は、GHQ経済科学局(ESS)の労働課の二代目課長として、労働改革政策に従事した人物。ニューディール派(もしくは改革派)の一人であり、ある部分からはコミー(赤)とみなされていた。当時、コミュニストであったかどうかは、この本に答えがある。
著者は、本書が基本的には《回想録というべきもの》だとことわっているが、歴史書として読まれる意図をもって叙述を貫いている。原タイトルは『第三の転機 マッカーサー、アメリカ人と日本の再生』であるが、著者が「再生」よりも強い言葉で「革命」をイメージしていることは疑えない。「占領革命」という邦題は、したがって、内容に即した選択である。
本書は、占領期が、七世紀から八世紀にかけての中国文化受容、明治維新による開国につづく「三度目の」歴史激動だ、という説を提起する。その二つは、アメリカによるものだ。そこに明瞭に、コーエンの歴史認識がある。
私的回顧録ではなく、歴史書としてみるなら、特記すべき二つ特質がある。一つは、もちろん、占領政策の重要部門に関わった当事者による記録である点。もう一つは、念を押しておくが、著者が「革命」について語っている(主観的のみならず客観性を期待して)点。

本書は、時期的には占領前期、空間的には著者の活動したESSの動きを主要にあつかうが、その観点は、占領全般の歴史的意義を解明することろに置かれている。その点は揺るがない。
歴史の激動はしばしば身近に気づかれないふうに起こる、とコーエンは書く。そのことを、当時の芦田均首相との会話を引き合いに出すことで証明しようとする。芦田は、ロシア革命のペトログラードに大使館員として勤めていたが、すぐ近くで「世界を揺るがせた十日間」が進行していたことを「知らなかった」という。おかしな喩え話にも感じるけれど、著者のいいたいことはわかる。――「その時」日本に起こっていたのは革命だった。しかして、われわれ(占領者および被占領者)は、事態の本質を、その瞬間、見逃してしまった、と。
本書のクライマックスは、後半のなかばあたりに(いくらか早めに)くる。二・一ゼネスト中止である。ゼネスト決行は、日本社会に破滅的な混乱をもたらせたかもしれない。それが《マッカーサー元帥によるぎりぎりの救出によって》回避された時、日本国の「第三の転機」は、より安定した安全な進路に向かうことになった。
二・一ゼネスト中止に戦後史(占領史)のターニング・ポイントをみる説は、もちろん著者の独創ではない。定説から外れるものではない。注目すべきは、コーエンの文体、語り口なのだ。本書の行間に淡く隠された情念、それは日本の社会主義化への強固な期待だった。
事件の進行を追いつつ、著者の関心は、主要に、交渉をつづけた労働運動の指導者たちの「人間」に傾いていく。名をあげれば、聴涛克己(彼は白色テロで重傷を負った)と伊井弥四郎(中止指令を読み上げながら嗚咽した)。彼らを語る著者の文体はまぎれもない熱い共感を放っている。
(ただし、徳田球一のアジテーターぶりを、亡命列車でペトログラードに帰還したレーニンのフィンランド駅での演説になぞらえる一節は、まったく不正確だと思うが)。
こうした「回想」を読むと、吉田茂などか著者をコミーと批難した事実にもうなずけるものがある。この時期のコーエンがコミュニストであったかどうかは別にして、次の一点は否定できないだろう。――彼は、日本の社会主義化の可能性を信じていた(のみならず、GHQの一員として自分がその可能性を拡げることも出来ると密かに考えていた)こと。
これは、徳田や野坂参三らの日本共産党が一時称えた「占領下平和革命論」なる綱領とは、まったく別個のものだ。権力の側にいた者がいだく一個の白昼夢のようなものだったかもしれない。だが、その「回顧」を、著者は公にせずにはおれなかったのだろう。
その意味で、最も重要な、そしてまったく独自な記述は、「第十八章 消えた陸軍放出物資」である。
解体された旧帝国軍隊の財宝がどこかに隠匿されている、といった話なら、人口に膾炙しているし、いまだに小説のネタに使われたりする。それはそれとして、本書が、注目するのは、軍隊の備蓄物資、補給物資――平時の社会にも活用できる原材料もしくは製品などのことだ。軍隊は、さらに何年かの戦争継続の見通しのもとに装備を整えていたが、敗戦によってそれらの用途は消滅した。
《一度として動員されることのなかった約四百万の幽霊陸軍のための制服や装備などがそうであった(内務省が一九四七年末、私に提出した廃棄リストには四百万着の軍服、四百万着のズボン、四百万足の靴、四百万個の帽子、八百万足の足袋、百万個の毛皮の帽子が含まれていたと記憶する)》
この章には、こうした途方もない数字が延々とつづく。これらは「どこかに・盗まれて」しまったのである。占領軍に没収される前に、軍隊は膨大な物資を民間に「払い下げた」。払い下げたといっても、それは、経済活動ではない。「闇に消えた」のだ。そして、この時代のキーワードの一つに、闇市、ヤミ物資などがある。GHQはその物量の調査に乗り出そうとしたが、いったん「消えた」物資がもどってくるというのは、あまりに空想的すぎた。
大日本帝国が実現した軍事予算の巨大な数字を示した後、著者は、その予算によって調達された物資のかなりの部分が「未使用」に残っていたと記す。神風特攻隊などの影響からか、後代の(歴史に暗い)われわれとしては、敗戦に「刀折れ、矢尽きて」といったイメージを持ちやすい。だが、武器はなくとも、武器とは別に、物資は大量に備蓄されていたのだ。
本書は、これらの事実から、二つの結論を引き出す。
一、膨大な隠匿物資が、後の経済復興の原動力となったこと。
一、社会党内閣は、彼らの政策である基幹産業国営化のために、隠匿物資を活用すべきだったが、そこでも失敗した。
旧帝国軍隊による統制・計画経済が残した物資こそ、占領下日本という歴史上未曾有の社会にあって、資本の原始的蓄積そのものだった。――それが著者のコミュニズム認識だったといえよう。
もう一点、本書には、興味深いエピソードが記されている。将軍の暗殺未遂事件だ。車から降り、第一生命ビルに入ろうとしたところを一人の日本人に襲われた、という。男はMPに逮捕された。マッカーサーは彼の不満を聞き、釈放させた。事件も報道されなかった(ただし、これは、コーエンの伝聞による記述なので、裏付けはない。どんな武器で襲ったかもはっきりしない)。暗殺未遂という意味では唯一の出来事だったか。とはいえ、事実と断定することもできないのだ。
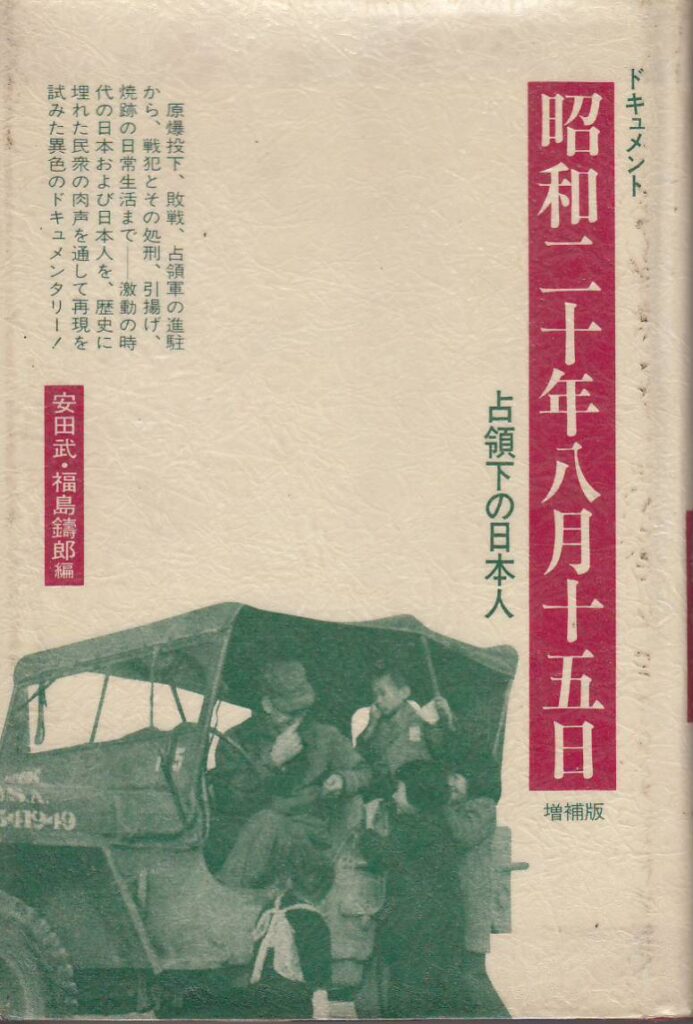
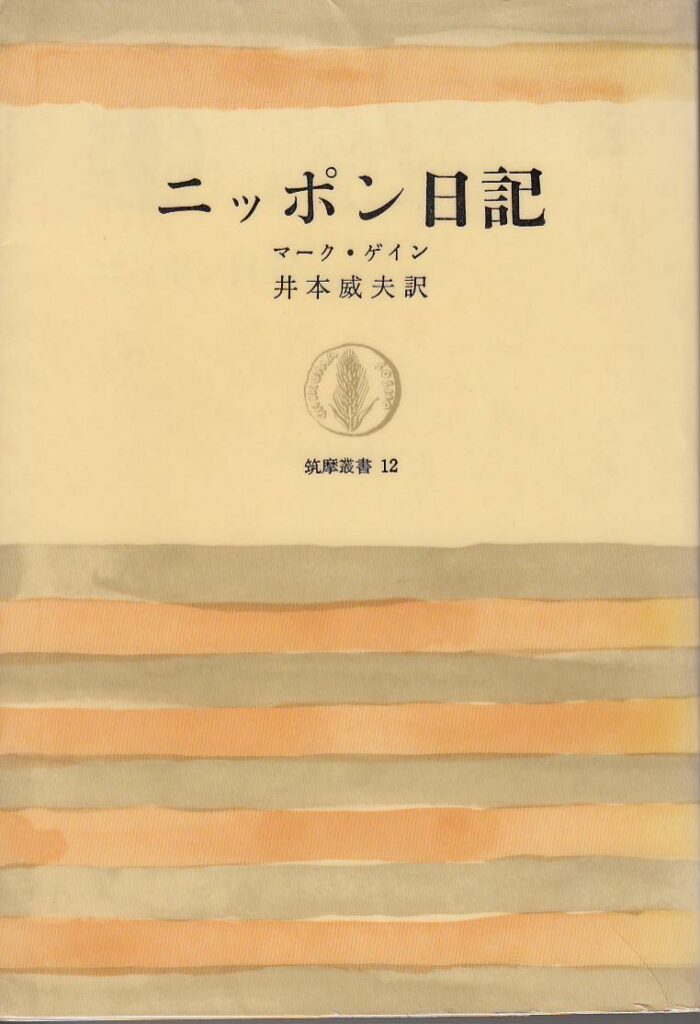
筑摩書房 1963.1
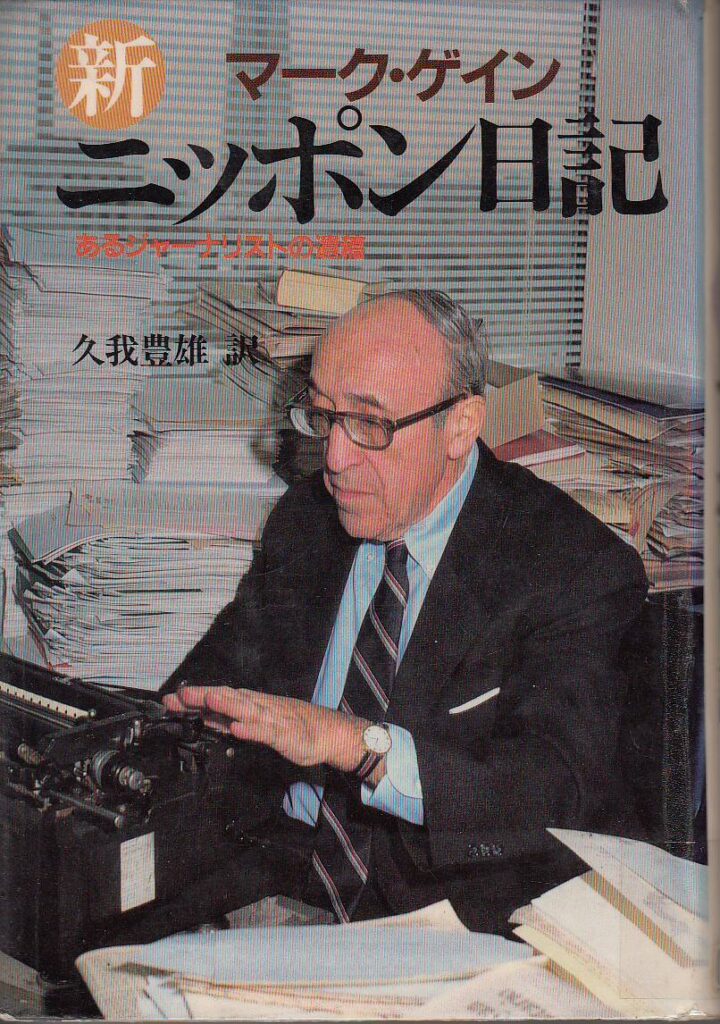
(2016.11.29執筆)
コメントを送信