思想の科学研究会編『共同研究 日本占領軍 その光と影』

第29回 思想の科学研究会編『共同研究 日本占領軍 その光と影』
『共同研究 日本占領軍 その光と影』は、思想の科学研究会による前著『共同研究 日本占領』の続編、増補版といえるものだ。前著の刊行後にはじまった第二期研究会六年の成果としてまとめられた。
本書は一冊に収まらず、上下巻に分かれ、さらに、副産物として『日本占領研究事典』も加えた。事典は、本土編と沖縄編から構成されている。


研究のスタイルおよび、個別筆者による多様な報告形態は、前著と変わっていない。より包括的な論考を立てるのと同時に、前著を補う各論の項目も増加している。編者は、今回の収穫として、専門的研究者による共同作業が得られたことをあげている。前著と合わせて、セットになった研究書として利用されるべき書物である、といえるだろう。
あるいは『共同研究 日本占領』を予告編のようなものと捉え、本書のほうを本格的な研究書の成果として受け止めることも出来るだろう。
各論的な方向でつけ加えられた項目は多岐にわたる。「部落解放運動と占領」という視角から朝田善之助の証言が採録されている他、日本共産党幹部の証言として、前著の神山茂夫につづいて、志賀義雄が招かれている。


研究会の中心的牽引者であった佃実夫は、下巻の長いあとがきに、私的な回想も取り混ぜてさまざまなことを書きこんでいる。
その一節を引こう。
《わたしたちが第二期と呼んでいる共同研究を再開した頃、まだ元気で、熱心に″研究例会″に出席し、地声であるらしい大きな声で議論を吹きかけ、その大声ゆえに、ほとんど″研究例会″の論議の流れを支配するほどだった呉林俊〈オ・リムジュン〉が突然、病死した。四七歳だった。
一九七三年(昭和四八)九月三日のことである。
その年は例年に例をみないほどの猛暑で、翌四日、横浜でおこなわれた葬儀の日も、耐え難く暑い日だった。サークルの仲間に知らせるまもない急死だったが、加太こうじ、久米茂、袖井林二郎らが、新聞の死亡記事を見て葬儀に駆けつけた。
前著『共同研究・日本占領』に「占領と朝鮮人」の好論文を寄せてくれた彼は「続篇」では「もっと深みのある、いいものを書く」と張り切っていたのだが……。葬儀の終った翌五日から、急に涼しくなったのを鮮やかに覚えている。……占領と朝鮮人の問題だけではなく、在日朝鮮人の一人として、呉林俊には書きたいことが山のようにあったに違いない。その情熱をはらんだまま、その夏の熱気まで持ち去るように彼は逝った》

なお、原文の人名には「ごりんしゅん」という日本語読みのルビが付されていた。
わたしは、前著の文章から、呉林俊は共同研究会のメンバーではないと判断していたが、佃の回想によれば、第二期の例会の初期に参加していたわけだ。
いずれにせよ、呉林俊の早逝によって、彼の肉声(けっして物理的な大声によってではなく)が研究会の方向に強い影響を与える可能性は断たれた。
そして、残ったのは、在日朝鮮人からの観点をふくまない占領日本研究は不備であるしかない、という厳然たる真理だった。
思想の科学研究会占領研究サークルと呉林俊との「出会い」は偶然に属する出来事であったのかもしれない。だが、その遺産は、大きく、深く、しかも持続的なものだった、と思える。
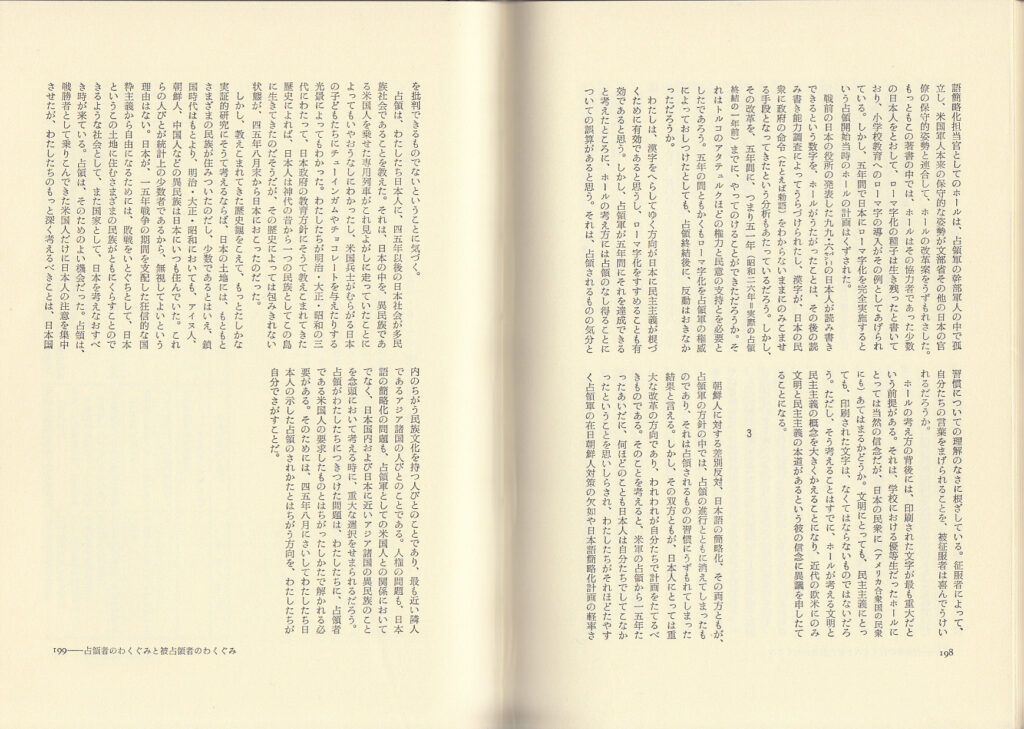
沖縄に関しても、いえるのは、まったく同様のことだ。沖縄人の研究者の参加をみないかぎり、その視点は、本土人に限定されたものになるしかない。
本書は、下巻に、大田昌秀と竹前栄治による長い討議を収録し、事典に「沖縄編」を立てることによって、本土と沖縄の「共闘」を模索した。その試みは、貴重なものだ。
また、佃は長いあとがきで、第一期から十年つづいた研究会の「一三八回」すべてに出席しえたことを、誇らかに記している。
本書の刊行から、約半年後、佃は、早すぎる死に襲われる。五三歳だった。共同研究の《熱気を持ち去るように彼は逝った》とするのは、後代の僭越な感傷にすぎるだろうか。
GHQ資料室 占領を知るための名著・第29回  2017.01.01更新
2017.01.01更新
『占領を知るための10章』第七章下書き (2016.11.15執筆)
コメントを送信