久生十蘭「母子像」

第25回 久生十蘭「母子像」
久生十蘭の晩年の作になる「母子像」は、10数ページの短い小説だが、そこにこめられた寓意は、その容量をはるかに超えている。深読みはいくらでも成り立つ。あるいは、そのことは、対象が十蘭だからこそなのか。あっけない結末ながら、その意味は底知れないようにも思える。巧緻の技芸家十蘭ならではの、手のこんだ仕掛けなのだ。
話は、進駐軍厚木基地近くで不審な行動をとった少年が保護されるところから始まる。犯罪に関わったわけでもなく、官吏たちは、少年をどう扱っていいのか判断しかねている。
前段で、少年相談員と少年の担当教師の会話をとおして、彼の十六年の生が素描される。和泉太郎。サイパン島生まれ。終戦時、母親の手にかかって殺されかけたことがある。頻発した集団自決の試みとは違う。ただ、首を絞められ、樹の下に転がされていた。
中段は、太郎の回想によって、サイパン最後の日のことが描かれる。
後段は、現在。警察署の保護室。教師の投げかける詰問というかたちで、少年の最近の行状が並べられていく。太郎は答えないが、作者は、その愚問をせせら笑う少年の内面を、最小限明らかにしてみせる。教師は「ヨハネ」という仇名(初稿では、沖縄人の設定だったというが、決定稿では省略されている)。ヨハネだけでも、寓喩は充分とみなされたのか。
母は銀座でバーをやっている。少年は、朝鮮から輸送機で運ばれてくる兵士たちを、タクシーに乗せて母親のバーに連れていく。頼まれたからではない。自発的な行為だ(時代は、朝鮮戦争の頃だと、さりげなく指定されている)。
戦後数年。「終戦」時、死に直面させられた子供は、生長の途をつかみ損ねた。彼の内面にあるものは、貧しい自殺願望であるばかりだ。埒のあかない教師の詰問に苛立ちを募らせ、ついに太郎は「死刑にしてくれ」と叫ぶ。自分の口から発してみると、幼い精神にとって、それは妙案であるように思えた。このような少年(見捨てられた実存)の始末は国家がつけるべきなのだ。国家以外に始末できるはずもない。そうではないか。
そこは警察署なのだった。折よく、手近に放置された拳銃を見つけた太郎は、それを手にして闇雲に引き金を引く。応射した警官の弾丸が、彼の望みをかなえた。
《太郎は壁に凭れて長い溜息をついた。だしぬけに眼から涙が溢れだした。そうして前に倒れた》
「母子像」は、1955年『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙主催の世界短編小説コンクールで第一席を受賞した。これには、十八カ国から七十篇が集まった。日本からは他に、石川達三、永井龍男、井上靖が参加した。本作の英訳は吉田健一。
最初から、外国の読者を想定して書かれた作品なのである。
さて、簡単にストーリーを要約したのみでも、作品のモチーフは明らかになっているだろう。深読みとは言葉の綾で、じっさいは棒読みしても伝わってくる。テーマは「反・占領」である。問題は、その先だ。この作品に明確な、占領社会への抗議が読み取れるのか否か。その点が明確でなければ、「母子像」は、たんなる占領期風俗小説として読み流されて終わる。それ以上の読みこみは、論者の恣意と受け取られかねない。
問題は、久生十蘭という作家の側にある。
久生は、戦時下、アメリカ人による日系人差別を素材とする『紀の上一族』を書いている。これは「鬼畜米英」の時代に沿ったイデオロギーを取り入れたもの。しかして、作者は、その一部を、六年の後(つまり、戦後)改稿し、シチュエーションを逆転させ、反軍国主義小説『ノア』の前半に組み入れている。
かなり大雑把にいえば、大衆作家としての久生は、「戦争迎合小説」の書き手の一人だった。白人帝国主義を敵視する「反米」小説の点数も多い。だが、その「迎合」の様態たるや……。
久生一流のスタイリストぶりを貫き、後代の読者を混乱させるばかりなのだ。ペダンチックな装飾好みに徹し、外国語(英語のみにかぎらない)ルビを多用する傾向は、戦時下にかえって増加した。戦時色の内容を、モダンな装飾的スタイルで語る、という異様な風俗小説を残した。
戦時下の代表作ともいえる『祖父っちゃん』は、昭和二〇年の新聞連載小説だが、佳境に入ったところで敗戦を迎え、さすがに中断のやむなきに到った。――この作品が全容をあらわすには、『定本 久生十蘭全集』発刊まで待たねばならなかった。六十数年の後である。作者の死からも、半世紀が経過していた。
久生は一九七〇年前後に異貌の「異端作家」の一人として復活してきた。現在でも、そうしたイメージの延長で、名手としての人気を保持しているだろう。だが、七〇年前後には、戦時下のイデオロギー的に判断微妙な作品は選別されていた。多くが「未発掘」のまま散逸していたこともあるが、復刻するにはあまりに「取り扱い注意」の要素が多すぎたのだ。
『定本全集』が完成した現時点でさえ、この作家の多くの作品は、解釈に細心の目配りを必要とする。評家にとっては厄介この上ない書き手として「現役」でありつづけている。
「母子像」は、反・占領小説として、かなりわかりやすい表層を備えた作品だ。しかし、その表層の奥に迫ろうとすると、作者の真意が疑わしくなるようなテクストでもある。小説は味読するものであり、解釈などは余計だとする一般論で済ませておくのが、無難な選択なのかもしれない。
しかし――わたしとしては、この難物作家を、ナチス時代の人気作家ハンス・ファラダ(本連載の19回で紹介)と比較してみたい欲求もあるが……。まあ、宿題のひとつにしておこう。
――「母子像」所収の本のうち主なものを次にあげておく。


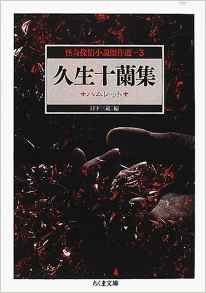




GHQ資料室 占領を知るための名著・第25回  2016.11.01更新
2016.11.01更新
コメントを送信