『「在日」の精神史』尹健次

第21回 『「在日」の精神史』尹健次〈ユン・コンチャ〉
全三巻、十章立ての思想史的記録である。だが、単一の年代記ではない。
本書の意図について、著者はいう。『「在日」の精神史』とは、「在日」の総体を歴史として記述することだ、在日朝鮮人の歴史・思想・精神を体系的に構築し、語りきることだ、と。
二つの祖国はありながら、他国に生き、他国の言語を使うことを強いられる少数民族集団。その生のすべては、逆に、豊かな総体の獲得への途をひらくだろう。
本書の体裁は学術エッセイに近いものだが、著者は、ひとつの「大きな物語」をめざす。叙述も、聞き書きを重視し、書物からの引用考察を主体とする方法ではない。この物語は、故に、未完であることを、あらかじめ限定づけられている。書物は成立しても、これは、あくまで中間報告なのだ、と著者は強調する。
本書は、「併合以降」の歴史をあつかうが、戦前の分には、一章が当てられるのみだ。明らかに、戦後の「解放」を基点として、この物語は構想されている。
在日の一世紀、百年をテーマとした類書はあったが、百年の通史というスタイルは、「宗主国日本人」を啓蒙する教科書にはなっても、在日を全的に語る形式としては最善のものではなかったようだ。
日本の敗戦時に、植民地朝鮮から渡航・渡日していた朝鮮人の数は、二百万ともいわれる。彼らは、論理的にいえば、「在日」であることからも「解放」されるはずだった。ところが、過渡的であったはずの「在日」という様態は、事実上の「永住」へと変容していった。
占領からはじまる戦後史の考察が、この変容に説得的な回答を示したとは思えない。日本一国という視点では限界がある。占領史研究は、旧植民地の「解放」がいかになされていったか(いかになされていかなかったか)を視野におさめることによって、充全なものになりうるだろう。
本書の観点は、当然、占領によって曖昧なまま流された「日本人の植民地責任」を糾すところに置かれる。「在日」の精神史は、〈日本の敗戦=植民地解放〉から真にはじまる。植民地時代三十六年を前史=序章として、この物語は語られていくのだ。
実質七十年余の歴史。かくも長き特別在留を強いられた民族共同体。分断祖国と日本、三つの国家のどれにも真に所属することが出来なかった。そして、各民族組織内の「小国家」にも、真の拠りどころは見つけられなかった。
たいていの朝鮮語(韓国語)の辞書には「在日」재일チェイルの語がない。あっても「日本にいること」という素っ気ない語義しか書かれていない。ZAINICHIという英語表記ほどにも「一般化」していないのか。
本書のような試みが受け入れられ、こうした物語が多く書かれねばならないのかもしれない。本書の構成は以下である。
第一巻 渡日・解放・分断の記憶
第二巻 三つの国家のはざまで
第三巻 アイデンティティの揺らぎ
著者の方法は、前著『思想体験の交錯 日本・韓国・在日 1945年以後』から継続している。一国、もしくは在日共同体のみの社会思想を考察し、関連づけても、新たな観点は立ち上がってこない。日韓朝の交錯をとらえる著者の姿勢は他に類をみない。だが、それは在日という苦難の「精神共同体」が逆立的に手にした結実なのだ。あらかじめ保証されていた「正統性」などではない。
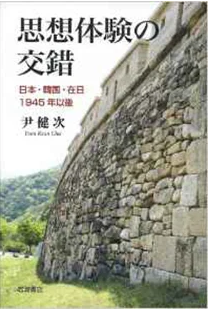
2008.7 岩波書店

2015.9 岩波書店

2015.10 岩波書店

2015.11 岩波書店
著者は、生の具体的現実を重視し、おびただしい数の在日群像の共同の物語を提起した。日本占領研究にとっても有益な発見が多くあるだろう。
ただ、この大著のすべての部分に首肯できるわけではないことは、最後に書き添えておく必要がある。一、引用文献に語らせ、著者の考えがよく伝わってこないところ。前著では、かなりの箇所にみられたが、本書でも、まだいくらか残っている。一、重要な文学作品を通り一遍の読みこみで済ませているところ。一、どう考えても不要のプライバシー記述があるところ。
もちろん、これらは、この「未完の物語」にとって致命的なマイナスというわけではない。大著であるがゆえに、細部のささいな違和感が残ってしまう結果にすぎない。
GHQ資料室 占領を知るための名著・第21回 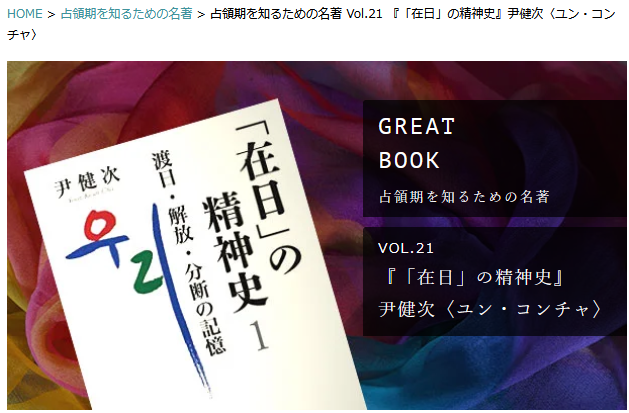 2016.09.01更新
2016.09.01更新
コメントを送信