『下山事件 最後の証言』柴田哲孝 前編

第5回 『下山事件 最後の証言』柴田哲孝 前編
下山事件は、1949年7月6日に起こった。戦後史最大の謀略事件として記憶される。他殺説自殺説が横行し、その「論争」は今もつづいている。
松本清張の『日本の黒い霧』が、占領軍による謀略説をとったのは1960年、戦後15年の時点だ。ちなみにこの年は、事件後11年、日本国独立後8年、殺人罪時効発効に後4年にあたる。占領の傷痕がいまだ消えない時代相にあって、先駆的な歴史解釈の足がかりを残した。
本書は、謀略のなかの暗殺説をとりながら、その実行主体については、いっそうリアルな分析を加えている。GHQも一枚岩の組織ではなかった。占領軍権力の内部抗争に加えて、相反する勢力の傘下にあった日本人組織の独自の動きがあった。彼らはGHQに利用されることによって延命をはかった大日本帝国の特務機関員だった。
ある種の政治家、官僚がそうだったのと同じく、戦争犯罪者でありながら、その特殊能力(人脈や資金力や諜報技能、あるいは生物兵器開発など)によって、権力システムの一角に寄生する場処を得た。彼らはGHQに利用されたというよりも、むしろGHQを利用し、自らの利権構造を強固に上乗せしていったのだろう。
下山事件はその途上に起こった。
黒幕であるGHQ(GⅡ)にとって「暗殺」は、まったくの想定外だったようだ。GⅡがGSとの権力闘争に勝利した時点だったが、1949年段階でのアジア情勢の変化、アメリカ本国の戦略見直しを考慮すれば、その権勢は安定したものとはいいがたい。
また、新興諜報組織であるCIAも対抗してきた。後に下山事件への関与を取りざたされるキャノン機関などは、錯綜する内部抗争の大きな要素だった。
こうした諸勢力と日本人「下部」機関が入り組んだ闇のネットワークを構築していた。その実相の一端もじょじょに暴露され、「占領軍による謀略」説の単一な構図は、次第に過去のものとなっていく。
本書は、ここに、亜細亜産業という組織を浮かび上がらせる。表向きは貿易商社(麻薬マネーが示唆されるが、実証は出来ない)だが、その実態は不明だ。とにかく、そこに集まってくる政財界人の名簿が、ある種の「猛烈な臭気」を発してくる。
謀略暗殺としての下山事件の立案(かつ実行)は、この亜細亜産業に出入りする諜報員によってなされた――とするのが、本書の立場である。
当時の国鉄は、旧満鉄を吸収した巨大企業、巨大な利権システムとして屹立していた。表向きは、膨大にふくれあがった傘下労働者を削減するための合理化案――大規模な人員整理が第一の急務とされた。下山定則がその初代総裁についたのも、一には「首切り役」の任務のためだったという説もある。その当否はともあれ、下山を中心に、日米の闇の謀略計画が動きだしたことは否定できない。
それ故、事件を解くキーは、謀略そのものにではなく、それを胚胎した権力構造のダイナミックな変容にあるだろう。ここに注目すれば、敗戦から占領という日本社会の転換点にあって、連続面と断絶面とのはなはだしさが見えてくる。支配層は入れ替わったとはいえ、入れ替わらなかった勢力が在った。
下山事件の背後にいた実行グループにとって、戦後という断絶面はかぎりなく小さい。彼らは彼らの寄生することの出来る謀略世界に寄生しただけで、その本質を変えていないし、変える必要にも迫られなかった。当該社会に(特殊工作の)謀略要素がもしなければ、それをつくりだせば済むことだ。
その意味で、本書が展開する謀略説の説得力は殊のほか強い。
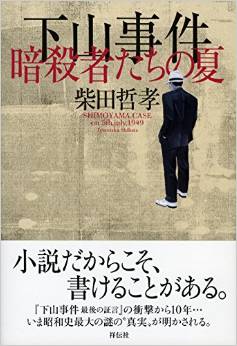
もう一点、他の類書にはない特色をあげておこう。それは、著者が「事件の関係者」の末裔である、という事実だ。
戦後まもない生まれの世代には、多かれ少なかれ、親たちの世代から様々な戦争体験の断片を聞かされた体験を持つだろう。それとは逆に「決して語ろうとしない」人たちも存在することをも、体験的に知っていったはずだ。
本書の著者も、近親の「決して語られない過去」に突きあたったのである。
後編につづく
GHQ資料室 占領を知るための名著・第5回 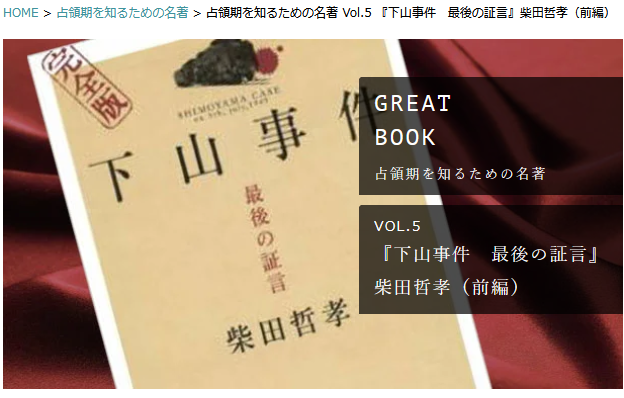 2015.12.15更新
2015.12.15更新
コメントを送信