『下山事件 最後の証言』柴田哲孝 後編

第6回 『下山事件 最後の証言』柴田哲孝 後編
本書の出発点は、著者の祖父が事件の実行グループにいたのではないか、という疑問から発している。
そのことを口にした大叔母の一言。「もしかしたら兄さんが……」。続く言葉をさえぎった大叔父のふるまいの不自然さ。二人は亜細亜産業の従業員だった。そして、亜細亜産業はごく「身内」の人間しか雇わなかったのだ。
ひとつの事件に心血をそそぎこむドキュメンタリ作家は珍しいケースではない。しかし、本書のように、真相が霧の彼方にある事件について、自分の血族(複数)が「犯人」だったかもしれない、という結論にいたるケースは稀有だ。当然のことに、この点は、本書に最大の迫真性を与えている。
著者の祖父は日誌を書き遺していたらしい。だが、それは、祖父の死後、祖母によってすべて焼却されてしまったという。祖父に可愛がられていた著者も、生前の祖母から事件にふれる話を聞きだすことは出来なかった。
「彼ら」は事件の謎を墓場まで抱いていった、というのが、血族の末裔である著者のなまな感情だった。
著者は、しかし、祖父の名を利用し、亜細亜産業のリーダー矢板玄に会い、一回かぎりのインタビューを試みる。老いた矢板の最初の印象を《戦国時代の武将》のようだった、と著者は記す。このインタビューの模様を伝える第三章は、本書の白眉といえよう。
長い会見が終わった別れぎわに、矢板は、「おれの目の黒いうちは下山事件について書くな」と芝居がかった科白を投げつける。事件への関与を間接的に認めたような言い草だ。少し出来すぎたシーンのような気もしないではないが、これが本書に特有の語り口なのだ。下山事件が自らの血族(のなかで特別の存在だった祖父)を傷つけたという感情こそ、明示されはしなくても、本書の基底に沈められた恨みにみちた哀しみなのだ。
とはいえ、著者はひとつの血族の物語を描こうとしたのではない。むしろ、そこから最大限、身を引き離そうと抗ったのだろう。
著者が建前とするのは、(もちろん)真実を糾明し、広く世に知らせようとするジャーナリストとしての使命だ。下山事件に「取り憑かれた」先達のジャーナリストへの共感、尊敬の念は、随所にしたためられている。その一方で、功名心に駆られ、著名事件を追うことによって売名を目論む同業者への侮蔑も隠さない。著者は、「自称映像作家」某が証言を捏造した手口を暴いているが、その例証の論点は、個人的な想いとは別のところにある。
あまりにもニセ情報が多いこと。それが、下山事件の見逃せない特性だ。事件には、後からつけ加えられた「怪情報」があまりにも多い。それらの一つひとつを丹念に吟味していけば、意図的になされた情報リークに共通する「シナリオ」が透けて見えてくる、と著者はいう。それは、自殺説を補強する証言であることがしばしばだ。
九割の真実に一割の虚偽をまじえ(たいていは、日時・場所をずらせ)ることによって、別の物語に誘導していく。――これは、スパイ・ストーリーの定石でもあるが、下山事件においても多用された。
著者によれば、意図的なリークを受けたのは、執念をもって下山事件を追っていたジャーナリストだった。記者が「騙されて」ニセの事件シナリオを流布したということだ。下山事件の奇怪に入り組んだ「全貌」の多くの部分は、こうしたニセ情報の氾濫によっていたずらに肥大するばかりなのだった。
あらずもがなの疑問をひとつだけ呈しておこう。――下山ははたしてそうした謀殺のターゲットたる充分な要件をそなえていたのか、という点だ。戦後過程にかぎれば、要人テロの件数は、驚くほどに少ない。下山が暗殺の的にされるほどの重要人物だったかどうかは、腑に落ちないことだ。戦後社会に特有の現象とは、いわゆる政治テロリズムが右翼による白色テロに塗りつぶされてしまったことではないだろうか。だが、下山には白色テロの標的とされるようなイデオロギー的背景はない。
なぜ初代の国鉄総裁がマトにされたのか。その点を解明する有力な説はあらわれていないのだ。
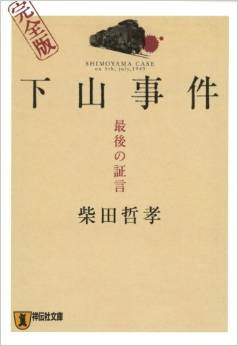
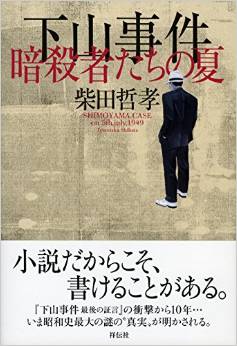
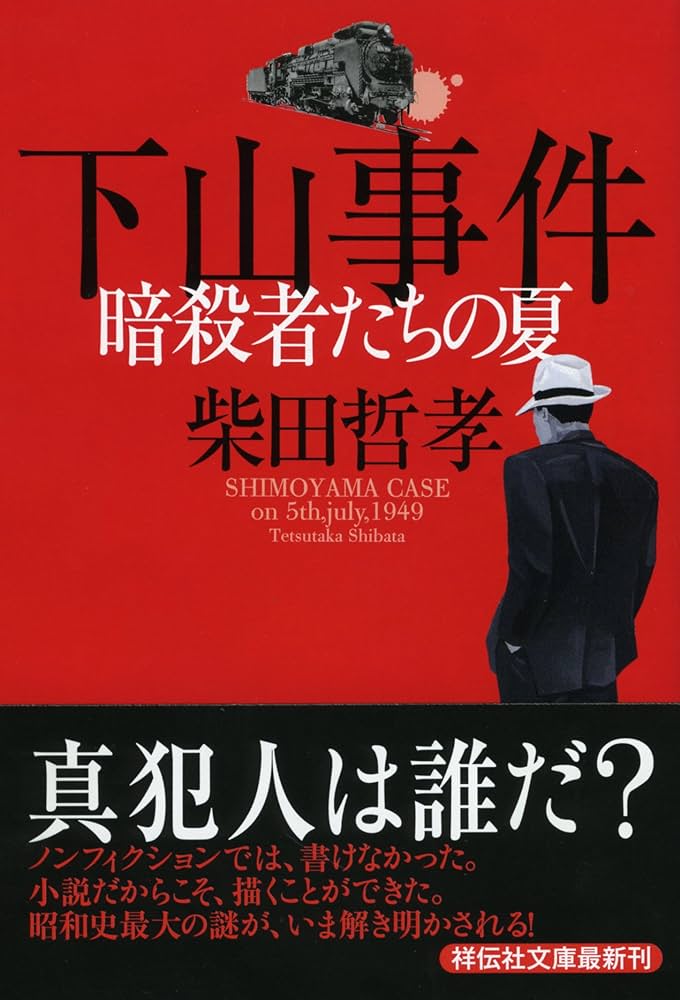
本書は、2005年に刊行され、日本推理作家協会賞を受賞した。2007年刊行の文庫版にはそれ以降に得たデータも加筆され、「完全版」と銘打たれている。
さらに著者は、2015年、同一の内容を小説化した『下山事件 暗殺者たちの夏』を問うた。
GHQ資料室 占領を知るための名著・第6回 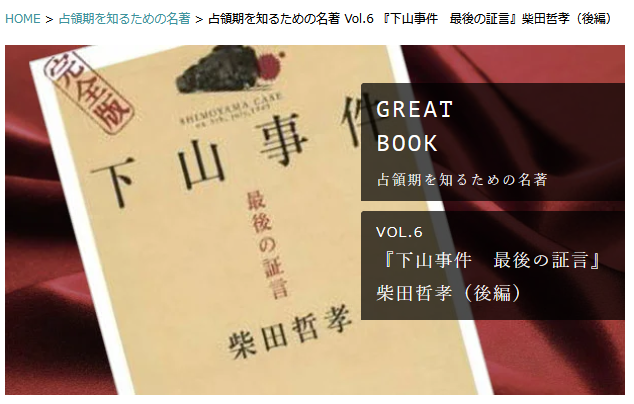 2016.01.01更新
2016.01.01更新
コメントを送信