『占領期雑誌資料大系 文学編Ⅳ』より金胤奎「ある父子」
第8回 『占領期雑誌資料大系 文学編Ⅳ』より
金胤奎「ある父子」
金胤奎〈キム・ユンギュ〉といっても、知る人はごく少ないだろう。
立原正秋といえば、かつての流行作家の名を記憶している人は多いと思う。金胤奎は、その立原の民族名だ。
立原は、自らの出自を「混血の日本人」と述べ、朝鮮民族の血はさかのぼって貴族の祖先にいたると記していた。「混血の日本人」とはつまり「混血の朝鮮人」でもあるわけだが、朝鮮民族の血は「より少なく」由緒ある高貴のものだと誇ったのである。
だが、自筆による経歴は一個のフィクションに他ならなかった。彼は朝鮮の農民の(純血の)出であり、生涯、生まれた土地を再訪することはなかったという。詳しくは、友人の高井有一による愛惜に満ちた評伝『立原正秋』およびその文庫版解説(尹学準)を参考にされたい。
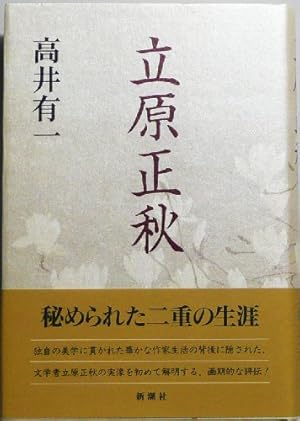
立原のアイデンティティの虚飾は剥がされてしまったが、彼の民族名による創作作品は、その死後も見つからなかったのだろう。というより、民族名による創作作品が在ったことすら知られていなかった。
プランゲ文庫の所蔵資料を復刻する過程で、発見された短編小説「ある父子」一篇が活字化されることになった。
発表は「自由朝鮮」1948年2月。
占領がつくった資料的盲点の具体例。それが、ここにもある。
プランゲ文庫とは?
占領期に興味を持つ者なら必ずつきあたる名前だ。
ゴードン・W・プランゲは、GHQ参謀第二部の戦史室主任歴史課長の職にあった人物。集まった刊行物は、1945年9月から49年11月までのもの。書籍は7万1千点、雑誌・定期刊行物は約8万2千タイトルあった。これらの多くを、プランゲは、自らの勤務地であるメリーランド大学に譲渡させた。
国内では見つからない資料も多く、プランゲ文庫は、占領期研究の基本的なデータベース提供源でありつづけている。その時期に刊行された書物が国外に流失し、かつ一元化されているという事実こそ、占領時代の本質的側面を語っている。
独立国家ではなかったのだから当たり前といってはそれまでだが、占領下における言論弾圧をことさらにいい立てることは、一面的な議論にしかならないだろう。資料の欠損のために解釈を誤る現代史研究は少なくない。
現在では、国立国会図書館との提携により、活字資料のマイクロフィッシュ化もすすみ、手軽にアクセスできる環境がすすみつつある。
また『占領期雑誌資料大系』(全十巻、大衆文化編・文学編、各五巻)が、2008年から10年にかけて刊行された。
本稿の記述は、その文学編Ⅳ『「戦後」的問題系と文学』にもとづいている。
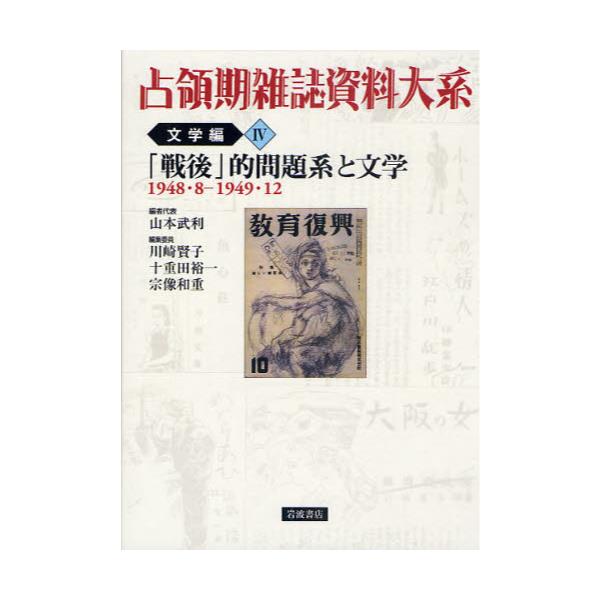
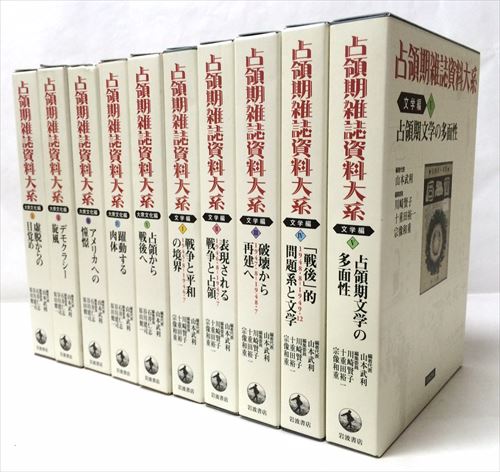
さて、立原正秋にもどろう。
「ある父子」という短編は、いわゆる初期習作といったものであり、作家研究にたずさわる者にとって、意味ある文献ではあるだろう。それ以上の意味を見つけることは難しい。
ここでは、作者が民族名で発表し、かつ、素材的にも民族色を露出させていた点に注目したい。評伝『立原正秋』には、野心に満ちて作家的階梯をのぼっていく作家像が身近な眼から観察されている。発掘された「金胤奎時代」と、日本文壇での成功をめざす「立原正秋時代」とでは、明らかに段差があるのだ。
立原は、前回にとりあげた金石範と同世代。同人誌に作品発表した(つまり、他に発表舞台を持っていなかった)時期も、ほぼ重なる。作品世界は隔絶しているが、近接した共同体を通過した同時代人であった。ただし、立原には、それ以前の注目にたりる文筆活動があった、ということだ。
ブランゲ文庫には、金胤奎名義のみでなく、金井正秋名、立原正秋名の作品が所蔵されている。彼はそれを隠したわけではない(経歴を虚構化したように隠したのだとしたら、興味深い性格ドラマを提供したかもしれないが)。
結果として、隠された。占領下体制によって隠されたのだ。
占領下から独立を経る時期、在日朝鮮人文学の軌道はどういうコースをたどったのだろう――。この種の観点を介することなしに、一人の作家のケースを個別に詮索してみても虚しい。
金史良は朝鮮戦争で「戦死」を遂げ、張赫宙は民族的裏切者・親日迎合者の汚名の只中にあり(それを晴らすことは出来ず、野口赫宙あるいは野口稔として終わった)、戦後から50年代全般にかけて活動した作家として、金達寿の名があげられるにすぎない。在日朝鮮人が日本語で作品を発表していく展望は、かなり暗澹としたものだったろう。とりわけ、金達寿のようにイデオロギーへの忠誠心を明確に持っていないとしたら……。
民族の血の濃密さを全面展開するような文学を日本社会に発信することは果たして可能なのだろうか。植民地主義の清算を「免除」された均質な戦後日本社会に向かって、断固たる朝鮮人文学を問うこと。それは可能なのか。
立原正秋が選んだ答えは「否」だった。
占領下の言論統制は、彼の意図に都合よく、民族名で発表した習作を、結果的に隠蔽する方向にはたらいた(彼がそれを知っていたかどうかは、問題にならない)。
立原は「混血の日本人」という「仮面の告白」を決然と選びとるに到った。
虚構を張りめぐらせ、日本人と成る以外に、文学的栄達の途はない(と、彼は信じたのだ)。
その選択を「戦後版・野口赫宙」と批難した者はいない(少なくとも、立原の生前には)。
だが、そのような自己告発は、彼の内部には強固にあったのではないか。だれよりも立原自身が、自らの「民族的裏切り」を自覚し、苦渋を噛みしめていたような気がしてならない。
(野崎六助『魂と罪責』p42-51 参照)
プランゲ文庫から発掘された短い作品は、以上のような考察を、立原正秋について、つけ加えることを促した。
GHQ資料室 占領を知るための名著・第8回 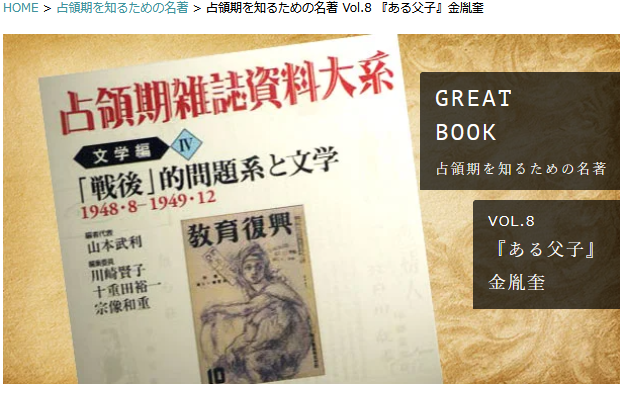 2016.02.01更新
2016.02.01更新
コメントを送信