『敗北を抱きしめて』ジョン・ダワー 前篇

第3回 『敗北を抱きしめて』ジョン・ダワー 前篇
本書『敗北を抱きしめて』は、1999年、新たな帝国主義と暴力の世紀がはじまろうとする直前に刊行され、2001年に日本語訳が実現し、広く反響を呼んだ。さらに、アメリカによる正義なきイラク占領と同時期の2004年、その増補版が再刊される。
この数年のあいだに現実のものとなった「世界変動」の重大さについて、著者は、増補版の序文において強調している。
同時に、その認識は、本書が広範に読まれ、戦後日本人の肖像を考察するにさいして不可欠の「古典」として日本人に受け入れられたことの確認でもあった。アメリカ人による「日本論・日本人論」は、古くは『菊と刀』がある。ダワーのこの書物は、刊行数年にして、『菊と刀』を凌駕するほどの評価を得たといっても過言ではない。
戦後の日本民族は、いかにして敗戦から他国軍隊による被占領という未曾有の「運命」に立ち向かい、それに適応していったのか。
本書が、歴史書として、アメリカ本国での評価のみならず、分析対象とした当の日本でも広く受容された理由は明らかだろう。
だが、かえって、そこにこそ、本書を全体として読みそこねる陥穽があるのではないか。その点をまず押さえておこう。
それは何か――。
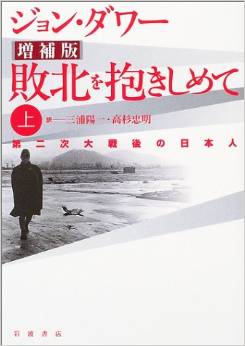

増補版の序文はいう。
《あれだけの悲慘と混乱の最中にありながら、なぜ、日本は無秩序と無縁であったのか? あれだけの激しい戦闘のあとに、なぜ、占領者に対する暴力がまったく発生しなかったのか? どのような事情によって、日本人はあの苦難を乗り越え、多様な創造性を発揮して「やり直す」ことができたのか? 戦後日本では、いったいどんな心理的、制度的、法的な変革、それも重要かつ永続的な変革が起こったのか?》
いいかえれば、著者は、ここに、誇りをもって「敗戦ー被占領」という民族存亡の非常事態を乗り切った一民族へのリスペクトを捧げている。
日本民族への尊敬の念。著者は、歴史家である以上、対象化された日本民族が抽象観念ではなく、一時代の歴史的存在としての在り方であったことを看過するわけではない。もちろん本書も、豊かな内容の詰まった多面的な歴史書である。
しかし、増補版の序文に顕になっているのは、本書を受け入れた「日本の読者」への、単一な感謝の念でありすぎるような気もする。著者自身が本書の内容を、誇りをもって単純化してみせた印象なのだ。ここで単純化が生じた由来は、単純にいって、著者の日本人論が「日本の読者」にとって快く受け入れられる歴史認識だったからだろう。
一部の勢力が命名した「自虐史観」なる汚い用語は、要するに、近現代史の暗部をリアルに見つめすぎるな、という警告にほかならなかった。ひるがえって、真摯な歴史意識が一民族への誇りを再生してくれるのなら、それは留保ぬきに歓迎されるべきだろう。「敗北に打ちひしがれた廃墟」からの出発をかかげた「左翼史観」が地に堕ちて久しい。それを感情的に非難する論点は、ますます多数化している。だが、本書が指し示したのは「敗北に打ちひしがれなかった」歴史の一断面だった。
単純化のもっと本質的な局面は、素朴にいって、ほとんどそのタイトルに拠っている。敗北を・抱きしめて。「敗北」という観念と「抱きしめて」という情緒的な能動との混合イメージ。そこに歴史が凝縮され、悲惨な一民族の(悲慘ではない)複雑な立ち姿が見えてくる。まさに、自己陶酔的な非合理性をしりぞけた理性的な歴史観の可能性が、本書によって示唆されたのだ。
著者によれば、本書は「スターティング・オーヴァー――やり直す」というタイトルで進行していた。焦土からの再出発。学術的でいかにも面白味のない歴史書をイメージさせる。書物の成功の多くの部分は、タイトルの喚起力によると思われるが、そのタイトルが本書を単純化することに帰結したのではないか。
もう一点、無視しえない単純化は、それは、著者自身によってなされている。それは、初刊の「日本の読者へ」に、すでに明らかだった。歴史書の方法として、著者は、知識人や支配層の言葉だけではなく、名もない庶民の言葉も重視する(たとえば、新聞の投書欄に載ったものを採録することをとおして)姿勢を広言している。これは当然の資料収拾ともいえる。つづいて、著者は、「日本人とは誰のことをさすのか」、誰を自分は研究対象とするのか、と自問し、「みんな」だと自答している。
つまり――あらゆる階層の日本人。「みんな」だ、と。
ここに、本書の本質的な欠陥があらわれている。
ここから、たとえば《そこにファシズムという言葉が一度たりとも出てこない》(『歴史と記憶の抗争』ハリー・ハルトゥーニアン)といったような批判が発生したのだろう。
「あらゆる階層の日本人」というダワーの理論モデルは、残念ながら、あの蒙昧な日本人単一民族説に近接していってしまう。
日本占領という歴史的ケースは、ずいぶんとわかりやすい歴史過程なのかもしれない。同時期に進行したヨーロッパ・ドイツと比較してもそう思える。複雑な因子を切り捨てても、それほど誤差は生じないだろう。あらゆる階層の日本人というもっともらしい抽象観念には、わかりやすさがつきまとう。
端的にいえば、ダワーの「日本」には周縁(マイノリティ)がない。中枢(マジョリティ)日本のさまざまな階層が雑多にひしめいているだけだ。それらは、圧倒的大多数ではあっても「みんな」ではない。ダワーの欲する意味においてさえ、「みんな」ではない。マジョリティとマイノリティの誤差は決定的かつ深刻だが、『敗北を抱きしめて』の方法では対象化できない。
本書には、沖縄、在日旧植民地人という、大きな、あるべき項目がない。欠けている。
「敗北を抱きしめる」ことからも排除された人びとへのアプローチがないのだ。
もちろん、知日家であり、人種差別思想に鋭敏な歴史家である著者が、そうした観点を持っていないはずはない、と思える。だが、本書をいくら「抱きしめても」あるべき項目はにはたどり着かないのである。
「3.11」以降にも、本書が喚起したような「民族の底力」的な誇りが再来したかのシーンに立ち会わされることがあった。その側面では、本書の「古典」的効用の価値は揺るがないだろう。
さて、批判することから紹介をはじめてしまったので、一段落する。このまま終わるわけにはいかない。
次回に、学ぶべき多くの点について考えていこう。
GHQ資料室 占領を知るための名著・第3回 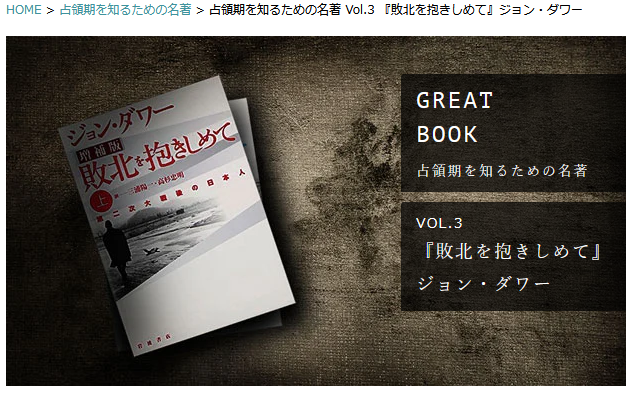 2015.11.06更新
2015.11.06更新
『占領を知るための10章』第九章下書き (2015.08.04執筆)
ジョン・ダワー 他の著書
1979 大窪愿二訳『吉田茂とその時代』
(各 上・下、TBSブリタニカ、1981年/中央公論社〈中公文庫〉、1991年、新版2014年)
1986 斎藤元一訳『人種偏見――太平洋戦争に見る日米摩擦の底流』(TBSブリタニカ、1987年)
改題『容赦なき戦争――太平洋戦争における人種差別』(平凡社ライブラリー、2001年)
1993 『昭和――戦争と平和の日本』(明田川融監訳、みすず書房、2010年)
2010 『戦争の文化――パールハーバー・ヒロシマ・9/11・イラク』
三浦陽一監訳、田代泰子・藤本博・三浦俊章訳(岩波書店(上・下)、2021年)
2013 外岡秀俊訳『忘却のしかた、記憶のしかた――日本・アメリカ・戦争』(岩波書店、2013年)
2017 田中利幸訳『アメリカ 暴力の世紀――第二次大戦以降の戦争とテロ』(岩波書店、2017年)



コメントを送信