萬朝報はわたしだ
第一章 萬朝報はわたしだ
黒岩涙香という稀有の人物を一行で尽くすなら、こうなる。ーー萬朝報はわたしだ。
西洋一九世紀の小説家なら、自分の小説の主人公の名に重ねて「ボヴァリー夫人はわたしだ」といった。いつしかそれが文学なるものの定式となり、教義までに舞いあがった。
しかしてわが明治のこの一代男は、自分の創った新聞に自らの全存在を重ねて、こう宣言した。萬朝報はわたしだ、と。誤解が生じると困るが、このとおりの文言を彼が書きのこしたという意味ではない。また、筆者の独断でもない。
この点についていえば、彼の三回忌に刊行された記念文集の「序」がいちばん近いことを記している。涙香会編『黒岩涙香』(一九二二)は、彼の仕事を調べるうえでの基本文献だ。《先生はその生涯の殆ど總ての善き部分を萬朝報に捧げられた。萬朝報は即ち先生の化身である》
化身、分身。どう表わしても同じだ。萬朝報はわたしであり、ぴったり重なる。余分も不足もない。
文学の教義が常識化してしまった社会にあって、こういう「わたし」を理解することはかなり困難だ。涙香はいわゆる小説家・翻訳家ではない。たんなるジャーナリスト・論説家でもない。それらの混沌未分を一身に体して生きた総合文筆家だ。時代とともに駆けた結果としてそうなった。
後代はこの「ともに」を体験しえない。だから彼をいくつかの分子に分けて整理したうえで理解しようと努める。ジャーナリスト、翻訳作家、探偵小説の元祖ーー。専門的研究者によるアプローチは一定の成果をのこした。しかし、分子化した分類学のままに放置するのは怠慢だ。もういちど彼を混沌未分のなかに戻してやらなければならない。萬朝報はわたしだ、と宣言する「わたし」とは何者なのか。彼の死から百年余を過ぎる社会に生きる「わたし」たちとどう違うのか。
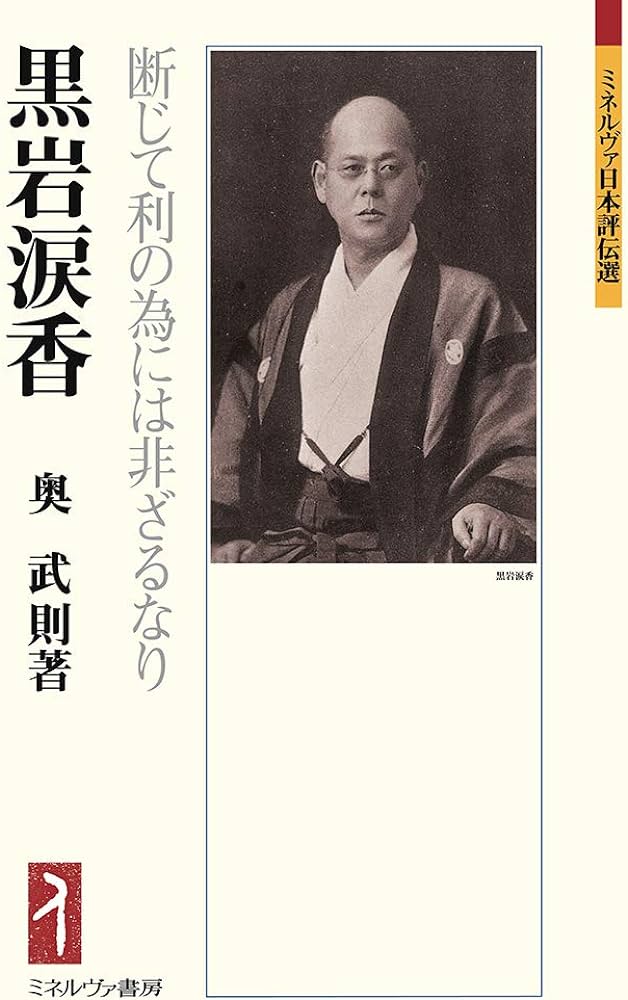


更新日記2023.10.09
涙香についての本を書き下ろすことになって、上記はその冒頭の試案。
コメントを送信